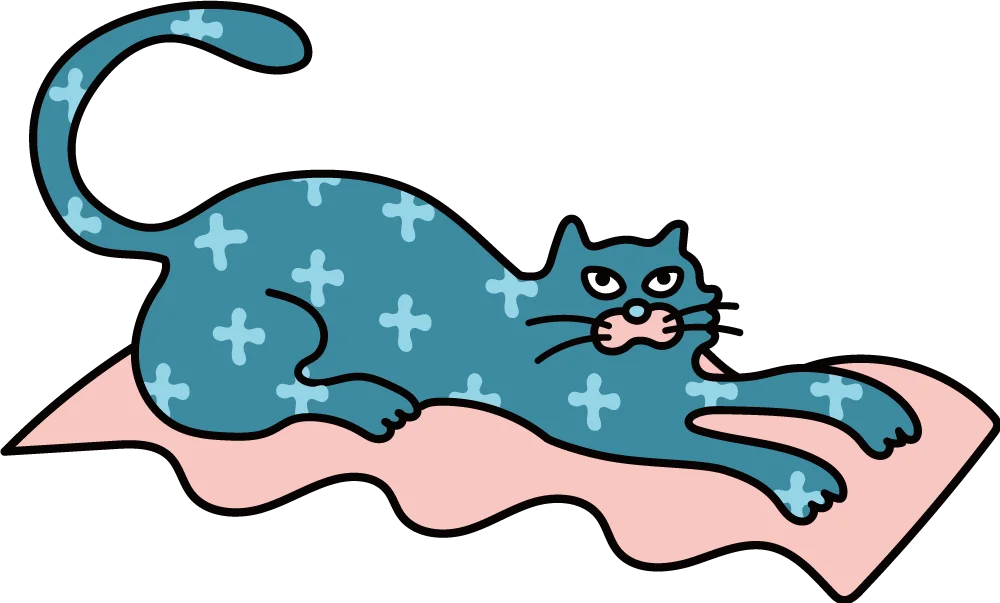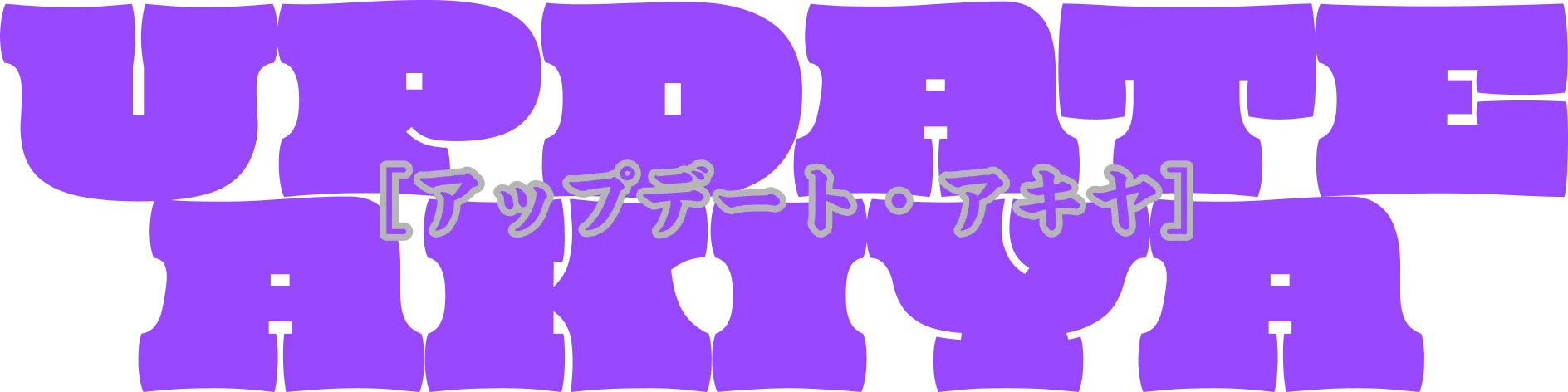空き家や中古物件を上手に活用したい。でも、いったい何をどうすればいいのかわからない……。
そんな悩みを抱えている人は少なくないはず。
そこで、このコーナーでは空き家・中古物件をうまく活用した成功体験を持つ“先達”たちが登場。
建物の修繕や改修に至るまでのプロセス、不動産業者や入居者とのコミュニケーション、利活用のためのアイデアなど、「空き家オーナーの目線」から体験を語っていただきます。
INDEX
京都に残る長屋の風景を残したい──住まい手とともに進める場所づくり。
今回「空き家活用体験談」にご登場いただくのは、かつては清水焼の窯元で賑わい、いまも趣深い長屋が建つ、東山区の「昭和小路」の再生に取り組んでいるIさんです。
長屋の改修はもちろん、地域の人たちとコミュニケーションを取りながら懐かしい路地のある町並みを残すべく奮闘するIさん。空き家の活用と同時に地域のまちづくりも進めるその活動について、お話を伺いました。
風景の継承は、住まい手や地域の方々とともに
——昭和小路はタイムスリップしたかのような懐かしく感じる町並みをいまに残していますが、この昭和小路の一帯を所有されているのですか?
全部ではありませんが、ほとんどそうですね。合計で22軒になります。
——法人として所有していらっしゃるんですね。
はい。もともとは祖母が所有していたのですが、相続することになったときに実家が経営している会社で買い取りました。僕が大学のときに建築を学んでいたこともあって、10年ほど前に両親から任されたというかたちです。

——長屋の改修はどのように実施されているのですか?
古いところは借り主さんが退去される際に改修しています。いまは路地奥にある4軒の長屋を改修中なのですが、3軒は若者・子育て世帯向けの職住一体の建物に、1軒はコモンスペースとする予定です。この路地奥の長屋再生は「昭和小路 ココナガヤ」プロジェクトとして、公益財団法人京都市・景観まちづくりセンターが実施する「令和6年度京町家まちづくりファンド改修助成事業」に選定されました。
——コモンスペースはどのように活用されるのですか?
地域の住民の方々のコミュニケーションの場だったり、このあたりはアーティストの方も多いので展示やイベントに使ってもらったり、地域と密接にかかわることができる場として活用できたらと考えています。
——昭和小路を盛り上げていこう、と。
そうですね。昭和小路は六原学区に位置しますが、六原まちづくり委員会さんの取組をはじめ、地域団体がとても活発な場所なんです。なので、昭和小路、ひいては六原にとって象徴的な場所になってほしいと思っています。

——地域の方々との合意形成や連携など大変なことはありませんか?
僕だけの力では難しかったと思うのですが、古くから住まわれている方が取りまとめをしてくださって。その方は昭和小路のことをとても熱心に考えてくれていて、僕の思いを伝えたら、「わかった」と受け止めてくれたんです。その方を通して、地域一帯の人たちともコミュニケーションを取れる環境ができています。
じつは、昭和小路が「建築基準法第42条第3項道路の指定*」を取れたのも、その方が中心となって動いてくださったおかげなんですよ。
道幅を広げず、町並みの風情を残す 昭和小路の「建築基準法第42条第3項道路指定」
昭和小路は約2.7m幅の細い道に京町家が建ち並ぶ路地です。本来、建築基準法施行時に家が建ち並んでいた幅員1.8m以上4m未満の道路は「建築基準法第42条第2項道路」と呼ばれ、建て替えの際は道路中心から2mの敷地後退が必要となり、道幅が広くなる分、敷地が減少し町並みの雰囲気が変わります。昭和小路は第42条第2項道路の特例となる「建築基準法42条第3項道路」の指定を受けることで敷地後退距離を「道路中心から1.35m」に緩和されることに。つまり、将来的に老朽化した建物を建て替えしたとしても道幅は現状とほぼ同じ2.7mとなり、京都らしい歴史的な昭和小路の町並みを維持することができます。
——地域の方も、昭和小路のまち並みを大事にされているのですね。
「京都に残る長屋の風景を残していきたい」という思いを共有できていることに、本当に助けられています。ただ、はじめからうまくいっていたわけではなくて、いちばん最初の改修のときは、まだ理解を得られていなかったような気がします。たとえば、改修したあとは家賃も上がりますし、どういう人が入居されるかもわからない。そうしたことに不安に感じる方もいたかもしれません。でも、新しい入居者の方々が積極的にコミュニティに加わってくれる人たちだったので、その問題はクリアできたと思います。
信頼できる専門家との協働で、一歩ずつ前へ
——入居者の募集はどのようにおこなっているのですか?
建築士さんを通して紹介いただいた京都R不動産さんにお願いしています。昭和小路のコミュニティについてご理解いただける方でないと住みづらいと思うので、そのあたりは事前に念入りにお話させてもらっていますね。
——設計や施工については?
設計は山本嘉寛建築設計事務所さん、施工は城南組さんでやってもらっています。城南組さんは昔から建物の修繕をお願いしていたのですが、山本さんは古民家の改修に強く、自分の
感性と合う建築士さんをネット検索で探しているなかで見つけて、実際にお会いしたときに「この人ならいろいろ考えてくれるはず」と思いました。
——今回、お邪魔しているこの物件も、外観は昔ながらの町並みに馴染みつつ、内観は暮らしやすそうにリノベーションされています。もとはどんな状態だったのでしょう?
60年ぐらい住んでいらした方がいた建物は、びっくりするほど荒れていて、とんでもないことになっていました。ただ、城南組さんや山本さんといった心強いパートナーがついていましたので、「なんとかなる」と思っていました。
——改修はどのようなかたちで進めていますか?
難しいところですが、まず建築士さんに入居者さんの想定について伝えます。たとえば、「この広さなら3人家族かな」といったような。そこから「3人家族やったら3つ部屋いるよね」とか「いや、2つで広くスペースを取ったほうがいいかも」とか意見交換したり……。この物件は、1階は無垢材をはって間取りの変更をしたりとこだわった分、2階をシンプルにしたのですが、そのアイデアもそうしたコミュニケーションのなかで出てきました。


——シンプルなベニヤの壁面に、歴史を感じさせる梁が印象的ですね。
ちょっと余白を残しているというか、入居者さんには壁紙を張ってもらってもいいですし。退去時も完全な現状回復を求めていなくて、次の入居者さんも入りやすいようなものにしてもらえたらOKというスタンスでいます。実際、1階のキッチンは、最初の入居者さんが設置されて置いていかれたものなんですよ。

——ちなみに、こちらの物件の改修費用はどのくらいかかりましたか?
ここを改修したのは5年前なのですが、当時で設計・施工を含めて1,100万円ぐらいでしょうか。京都市の補助金を活用できるかどうかなど、補助金はタイミングもあるし、毎年、必ずあるものでもないので、毎回、頭を使いながらやっています。
やっぱり現実的に問題になってくるのは、いちばんはお金の話なんですよね。空き家を所有されている方は、みんなそこに悩まれていると思います。
僕の場合は、京都R不動産の方とお話することで「投資したお金を何年でペイできるのか」というのを計算し、どれくらい費用をかけられるかを見極めています。モデルケースを見たりして、この点をクリアにできれば中古物件に投資しやすくなるのではないかなと思いますね。

——なるほど。では最後に、これから中古物件を活用しようとしているオーナーさんにメッセージや、今後考えていることがあれば教えてください。
「自分ひとりですべてを抱え込まないこと」ですね。建物の修繕など、すべてをひとりではできないですし、必ず誰かにお願いしないといけないから、頼ることが大事だと思います。
あと、今後のことで考えていることは、ブランディングをどうするかという点ですね。最近は物価が上昇し建築費も高騰しています。建築費が高くなると家賃に跳ね返ってきてしまうので、建築費を抑えながら家賃もあまり高くならないようにしたい。……バランスを取るためにも、昭和小路という一帯の価値をいかに高め、そして広げられるのかを考え、地域に還元していく必要があると思っています。インバウンド需要に頼らず、地域の人たちが賑わいをもてる場所にしていく。それが実現できるといいですね。